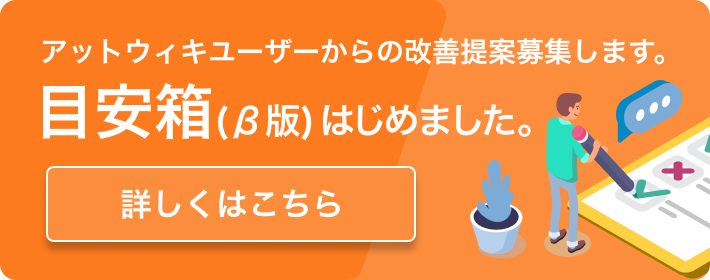ラノロワ・オルタレイション @ ウィキ
超難易度(レベルベリーハード)
最終更新:
匿名ユーザー
-
view
超難易度(レベルベリーハード) ◆LxH6hCs9JU
私の名前はシャミセン。猫だ。
世にも珍しい、オスの三毛猫をやっている。
ティーが、私の今のご主人様だ。白い髪に緑色の瞳が印象的な少女で、歳は前のご主人様と大差ないだろうか。
世にも珍しい、オスの三毛猫をやっている。
ティーが、私の今のご主人様だ。白い髪に緑色の瞳が印象的な少女で、歳は前のご主人様と大差ないだろうか。
そのティーだが、私を抱えたまま小さな台の上に立ち、両目にレンズ付きの筒などをあてがっている。
筒が伸びる先は窓ガラス、そしてその先に広がる光景は、夜景だった。
ここは摩天楼の上階、展望室。ティーの保護者である彼女、白井黒子が周囲を見渡すために訪れた部屋だ。
筒が伸びる先は窓ガラス、そしてその先に広がる光景は、夜景だった。
ここは摩天楼の上階、展望室。ティーの保護者である彼女、白井黒子が周囲を見渡すために訪れた部屋だ。
その白井黒子だが、ティーとは別の場所で望遠鏡を覗き、同じように街や、海の方角を眺めている。
表情はどこか険しく、覗き込む望遠鏡をしきりに変えてはなにか唸っていた。
表情はどこか険しく、覗き込む望遠鏡をしきりに変えてはなにか唸っていた。
「――これは夜だから、それだけのことなのでしょうか……いいえ、あれはおそらく夜が明けたとしても――」
見ていて忙しない。
私は、人語を介する猫として助言の一つでもくれてやろうかと思ったが、この身はあいにくティーに捕縛されてしまっている。
猫は犬と違って愛玩動物ではないのだが、幼い少女にそれを説いても無為というものだろう。
私は、人語を介する猫として助言の一つでもくれてやろうかと思ったが、この身はあいにくティーに捕縛されてしまっている。
猫は犬と違って愛玩動物ではないのだが、幼い少女にそれを説いても無為というものだろう。
白井黒子はひとしきり悩んだところで、ティーにここを発つと告げた。
摩天楼を離れ、別の土地に移動するつもりらしい。
私はどうすればいい、と尋ねると白井黒子は、
摩天楼を離れ、別の土地に移動するつもりらしい。
私はどうすればいい、と尋ねると白井黒子は、
「あら、いつの間に出てこられましたの?」
と言って私を再び、ティーの持つ黒い鞄にしまいこんだ。
強引ではあるが、私の抱き方が乱暴でなかっただけ大目に見るとしよう。
強引ではあるが、私の抱き方が乱暴でなかっただけ大目に見るとしよう。
さて。
この少女たちはこれからどこに向かい、誰と出会うのだろうか。
それは、鞄の中で丸くなっている私には知る由もないことだった。
この少女たちはこれからどこに向かい、誰と出会うのだろうか。
それは、鞄の中で丸くなっている私には知る由もないことだった。
◇ ◇ ◇
摩天楼の展望室で、この『世界』の景色を堪能した。
闇に包まれた市街地は灯りに乏しく、まるで全域が停電に見舞われたのような有り様だった。
海の向こうには灯台の灯りも窺えない、見渡す限り漆黒の水平線が伸びていた。
北西の山々は闇夜の中でもその深さが窺え、学園都市出身の彼女の目には新鮮な光景として映った。
闇に包まれた市街地は灯りに乏しく、まるで全域が停電に見舞われたのような有り様だった。
海の向こうには灯台の灯りも窺えない、見渡す限り漆黒の水平線が伸びていた。
北西の山々は闇夜の中でもその深さが窺え、学園都市出身の彼女の目には新鮮な光景として映った。
リボンで二本に結った髪を、馬の尻尾のように翻しながら進む、小柄な姿。
女物の学生服を着ており、右の袖には盾のようなマークを刺繍した腕章がある。
デザイン性に乏しい黒一色のデイパックを肩に提げ、纏う空気はどこか重々しい。
女物の学生服を着ており、右の袖には盾のようなマークを刺繍した腕章がある。
デザイン性に乏しい黒一色のデイパックを肩に提げ、纏う空気はどこか重々しい。
少女、白井黒子は高く聳える双頭の楼閣――摩天楼を背に、考え事をしていた。
考え事の種は、謎……にはなりきれない、小さな違和感。
街の造りを確かめるために上った展望室で、海のほうを眺めやったときに得たものである。
白井黒子はそこで、『黒』を見た。
街の造りを確かめるために上った展望室で、海のほうを眺めやったときに得たものである。
白井黒子はそこで、『黒』を見た。
(……夜空が黒いのはあたりまえ。月や星が出ていようとも、黒という色彩が変わることはありませんわ)
あれはなんだったのだろうか、と考えたところで答えは出ない。
答えは出ないと既に悟っているのに、考え続けている。
そう簡単に忘却できる違和感ではなかったから。
答えは出ないと既に悟っているのに、考え続けている。
そう簡単に忘却できる違和感ではなかったから。
白井黒子が見た『黒』は、常識的に考えて『夜』の『黒』だったに違いない。
海も街も、空も山も、『夜』が訪れればそれらは等しく『黒』に染まる。
月や星、街灯といった光源があったとしても、排除しきれない強烈な『黒』だ。
『夜』の『黒』は視界を不明瞭なものにし、映る光景に虚偽の情報を齎す。
きっと、海の向こうに見えたあの『黒』も、そういった錯覚の類だったのだろう。
海も街も、空も山も、『夜』が訪れればそれらは等しく『黒』に染まる。
月や星、街灯といった光源があったとしても、排除しきれない強烈な『黒』だ。
『夜』の『黒』は視界を不明瞭なものにし、映る光景に虚偽の情報を齎す。
きっと、海の向こうに見えたあの『黒』も、そういった錯覚の類だったのだろう。
そう、白井黒子は納得せざるを得ない。
今は、まだ。
今は、まだ。
(跳んで確かめに行く、というわけにもいきませんし。どのみち、朝になれば解ける謎でもありますの)
白井黒子が海の向こうに聳える『黒』を見て、抱いた違和感は三つある。
一つは圧迫感。レンズ越しに覗いているだけで、向こう側からこちらに押し寄せてくるような畏怖を感じた。
一つは奥行き。水平線などという珍しいものが見られたのはいいとして、どうにも近すぎるような気がした。
一つは空模様。雲はなく星々もくっきりと浮かび上がる空は、しかし海の方角を見ると黒一色になっていた。
一つは奥行き。水平線などという珍しいものが見られたのはいいとして、どうにも近すぎるような気がした。
一つは空模様。雲はなく星々もくっきりと浮かび上がる空は、しかし海の方角を見ると黒一色になっていた。
空模様など、そこだけ雲がかかっていたのかもしれないし、望遠鏡で遠視しきれなかっただけなかもしれない。
奥行きなど、そもそも夜の闇と漆黒の海面で元から曖昧な境界線だ。悩むだけ馬鹿馬鹿しい。
圧迫感など、単なる気のせいだ。とバッサリ切って捨てられる程度のものである。
奥行きなど、そもそも夜の闇と漆黒の海面で元から曖昧な境界線だ。悩むだけ馬鹿馬鹿しい。
圧迫感など、単なる気のせいだ。とバッサリ切って捨てられる程度のものである。
が、それらの違和感をすべて肯定したとすれば、脳裏に一つの仮定が浮かぶ。
その仮定すらも肯定してしまったとするならば、白井黒子は今度は違和感ではなく、本当に『謎』を抱える始末となるだろう。
その仮定すらも肯定してしまったとするならば、白井黒子は今度は違和感ではなく、本当に『謎』を抱える始末となるだろう。
(明かりの途切れる空、近くに感じてならない水平線、そして聳え立つような圧迫感……これでは、まるで)
――海の向こうに、『黒い壁』でも立っているようではないか。
(ありえませんわね。ありえたところで、なにをどうすると言うのでしょう。そりゃ、驚きはするでしょうけれど)
天から地まで、配られた会場案内図の四辺を覆う役割を、『黒い壁』が担っているとしたら――という、仮定。
我ながら突拍子もない考えだとは思うが、人類最悪の称する『主催者』なる者たちが、
なんらかの手段を使って『参加者』たちを隔離幽閉している、またはそれを望んでいることは明白。
我ながら突拍子もない考えだとは思うが、人類最悪の称する『主催者』なる者たちが、
なんらかの手段を使って『参加者』たちを隔離幽閉している、またはそれを望んでいることは明白。
だというのに、この会場図は一見して抜け穴が多い。
西の山々を越えた先、南東の海を越えた先、そこがどうなっているのか、まるで明記されていない。
閉じ込める、逃さない、この企画がそういった趣旨であるのならば、本来舞台となるのは絶海の孤島などが望ましいはずだ。
山や海を越えればどこに辿り着くのか、灯台や飛行場といった施設もあるのだし、ひょっとしたら――と考える輩を排除するために。
西の山々を越えた先、南東の海を越えた先、そこがどうなっているのか、まるで明記されていない。
閉じ込める、逃さない、この企画がそういった趣旨であるのならば、本来舞台となるのは絶海の孤島などが望ましいはずだ。
山や海を越えればどこに辿り着くのか、灯台や飛行場といった施設もあるのだし、ひょっとしたら――と考える輩を排除するために。
いや、もしくはそういった考えの輩を排除するための手段こそが、『黒い壁』なのかもしれない。
見渡す限り海一面、などというよりは、四方を壁で囲まれていたほうが絶望感もひとしおだろう。
見渡す限り海一面、などというよりは、四方を壁で囲まれていたほうが絶望感もひとしおだろう。
本当にそんなことが可能なのか、という疑問を棚に置いた馬鹿馬鹿しい仮説ではある。
その馬鹿馬鹿しさも、夜が明け、景色に光が宿れば、薄れて危機感に変わるかもしれないが。
どちらにせよ、朝になってもう一度空を眺めてみればわかることである。
その馬鹿馬鹿しさも、夜が明け、景色に光が宿れば、薄れて危機感に変わるかもしれないが。
どちらにせよ、朝になってもう一度空を眺めてみればわかることである。
(一つの謎にばかりこだわってはいられませんし、思考を切り替えるといたしましょうか)
白井黒子が次に考えるのは、摩天楼の正面入り口で聞いた、例の放送についてだ。
内容は挑発。放送の主はおそらく男性。位置は、声が反響していたために特定できない。
そう遠くはない位置、市街地のどこかからだろうとは思うが、探そうにも手がかりがない。
内容は挑発。放送の主はおそらく男性。位置は、声が反響していたために特定できない。
そう遠くはない位置、市街地のどこかからだろうとは思うが、探そうにも手がかりがない。
なので、考えないことにした。
予定どおり展望室で周囲の状況を確認し、暗くてよくわからないと結論を下し、摩天楼を発った。
そして辿り着いたのは、摩天楼からわずかに北、幹線道路が二つに分かれた、三角州上の道である。
予定どおり展望室で周囲の状況を確認し、暗くてよくわからないと結論を下し、摩天楼を発った。
そして辿り着いたのは、摩天楼からわずかに北、幹線道路が二つに分かれた、三角州上の道である。
白井黒子は道路上、前後に首を振り、どちらの道を行こうか思案する。
ルール説明を親身に聞いていた人間ならば、消滅するのが早い端っこのほうになどまず向かわないだろう。
とくれば、人が集まるのは必然的に中心部。ここは左に折れ、天守閣のほうを目指すべきだろうか。
ルール説明を親身に聞いていた人間ならば、消滅するのが早い端っこのほうになどまず向かわないだろう。
とくれば、人が集まるのは必然的に中心部。ここは左に折れ、天守閣のほうを目指すべきだろうか。
(人との接触の可能性が高い。つまり、それだけ危険度も高いということですけれど……あら?)
それまで、考察のすべてを頭の中で済ませてきた白井黒子は、ふと気づく。
自分の服のすそを、誰かが掴み引っ張っていた。
気づけ、という意思表示のようにも見られるその仕草の主は、小柄な白井黒子よりもさらに小柄な少女、ティーによるものだった。
自分の服のすそを、誰かが掴み引っ張っていた。
気づけ、という意思表示のようにも見られるその仕草の主は、小柄な白井黒子よりもさらに小柄な少女、ティーによるものだった。
特徴的なのは、白い髪と緑色の瞳。口は閉ざされており、彼女はなにを語ろうともしない。
けれど人見知りというわけではなく、白井黒子についてくるこのティーは、言うなれば超無口。
意思疎通を図るのに難儀しながらも、白井黒子はティーが見捨てられず、保護者などを引き受けていた。
けれど人見知りというわけではなく、白井黒子についてくるこのティーは、言うなれば超無口。
意思疎通を図るのに難儀しながらも、白井黒子はティーが見捨てられず、保護者などを引き受けていた。
「どうしましたの? ひょっとして、どこか行きたい場所でも――」
言いかけて、白井黒子は舌打ちした。
考察に耽っていたせいだ。その異臭に気づくのが、遅れた。
ティーは白井黒子よりも早くそれに気づき、こうやって知らせたのだ。
考察に耽っていたせいだ。その異臭に気づくのが、遅れた。
ティーは白井黒子よりも早くそれに気づき、こうやって知らせたのだ。
足下を見る。
見たところで判然としない。
暗がりのアスファルトはしかし、たしかに湿っている。
この湿り気の正体が水ではなく、灯油であるということには臭いで気づけた。
見たところで判然としない。
暗がりのアスファルトはしかし、たしかに湿っている。
この湿り気の正体が水ではなく、灯油であるということには臭いで気づけた。
(なんて古典的なっ、ブービートラップ――!)
気づいたときには、もう遅い。
白井黒子とティーが立つ道路に、火線が走る。
種火はすぐに燃え盛り、一瞬で業火へと成長した。
白井黒子とティーが立つ道路に、火線が走る。
種火はすぐに燃え盛り、一瞬で業火へと成長した。
◇ ◇ ◇
薄暗い夜道で、こうこうと炎が燃えている。
燃えているのは、近くの雑居ビルから拝借した灯油だ。
誰の所有物であったのかなどは知らない。
重要なのは、それが燃焼を手助けする物質であるか否かだけだ。
燃えているのは、近くの雑居ビルから拝借した灯油だ。
誰の所有物であったのかなどは知らない。
重要なのは、それが燃焼を手助けする物質であるか否かだけだ。
赤いポリタンクに入っている液体が、まさか墨汁などであるはずがない。
臭いだけを確かめ、それを幅の広い道路上にぶちまけた。灯油タンクの個数は一個や二個ではない。
周囲一帯は暗闇のため、近づく者もすぐには気づけないだろう。気づかれない内に、焼る――それが、彼女の算段。
臭いだけを確かめ、それを幅の広い道路上にぶちまけた。灯油タンクの個数は一個や二個ではない。
周囲一帯は暗闇のため、近づく者もすぐには気づけないだろう。気づかれない内に、焼る――それが、彼女の算段。
三角州近辺の幹線道路上で、ただ燃やすことだけに長けた魔術師見習い、黒桐鮮花は待ち伏せをしていた。
凛とした顔立ちには喜怒哀楽の色もなく、黙して炎を見つめる。
長く艶やかな黒髪が熱気によってぱさつくも、本人はそれを気にも留めない。
長く艶やかな黒髪が熱気によってぱさつくも、本人はそれを気にも留めない。
件の放送――いや挑戦状を聞いた黒桐鮮花は、あえてそれには乗らず、放送を耳にしたこの場に留まることを選択した。
彼女の目的は、最愛の兄である黒桐幹也を生かすこと。自信満々の大馬鹿者と正面切って喧嘩することではないのだ。
挑戦に乗るよりも、その挑戦を利用してやろう――鮮花が考え至った末に掴んだ『作戦』が、この待ち伏せなのである。
彼女の目的は、最愛の兄である黒桐幹也を生かすこと。自信満々の大馬鹿者と正面切って喧嘩することではないのだ。
挑戦に乗るよりも、その挑戦を利用してやろう――鮮花が考え至った末に掴んだ『作戦』が、この待ち伏せなのである。
おそらくは拡声器によるものだろう放送の発信源は、ここより西。
となれば、進路の都合上この道路を通らざるを得ない者も出てくるだろう。
挑戦に挑もうとする者、あるいは挑戦から逃げ帰ってきた者を闇討ちするには、もってこいの狩場。
三角州を望むオフィス街の一角こそが、黒桐鮮花の持ち場だと考えたのだ。
となれば、進路の都合上この道路を通らざるを得ない者も出てくるだろう。
挑戦に挑もうとする者、あるいは挑戦から逃げ帰ってきた者を闇討ちするには、もってこいの狩場。
三角州を望むオフィス街の一角こそが、黒桐鮮花の持ち場だと考えたのだ。
そして、獲物はのこのことここにやってきた。
彼女らが放送の主に会いに行こうとしていたのかどうかは定かではないが、そんなものは既に些事だ。
問題なのは、罠にかかった獲物を狩るか狩らざるか――鮮花はすぐに、狩るべきだと判断した。
彼女らが放送の主に会いに行こうとしていたのかどうかは定かではないが、そんなものは既に些事だ。
問題なのは、罠にかかった獲物を狩るか狩らざるか――鮮花はすぐに、狩るべきだと判断した。
だって、やって来た獲物は二人揃って『小さな女の子』だったのだ。
幹也が見れば、すかさず保護に回るだろう最悪の足手まとい。
可愛そうではあるが、幹也と出会う前に消えてもらわなければ。
幹也が見れば、すかさず保護に回るだろう最悪の足手まとい。
可愛そうではあるが、幹也と出会う前に消えてもらわなければ。
黒桐鮮花の行動理念は、すべて兄である黒桐幹也を中心にして形成される。
兄の生存に必要な存在であるか否か、己の手の内に余る存在か否か、判断は一瞬かつ容易だった。
兄の生存に必要な存在であるか否か、己の手の内に余る存在か否か、判断は一瞬かつ容易だった。
焼る。焼き消す。焼いて殺す。
バイオレンス極まりない思考は全部、幹也への愛情が肥大化した結果なのだと自己完結して、実際に焼った。
路上に満ちる灯油の端に、己が発火の魔術で軽く火をつけ、生まれた炎で少女二人を包み込んだ。
相手が逃げ切れるとは思えない。たとえ逃れたとしても、すぐに追って今度は至近距離から発火させるだけだった。
結果として、少女たちは逃げなかった。逃げる間もなく、炎に焼かれ、燃えて、死に絶えたのだ。
路上に満ちる灯油の端に、己が発火の魔術で軽く火をつけ、生まれた炎で少女二人を包み込んだ。
相手が逃げ切れるとは思えない。たとえ逃れたとしても、すぐに追って今度は至近距離から発火させるだけだった。
結果として、少女たちは逃げなかった。逃げる間もなく、炎に焼かれ、燃えて、死に絶えたのだ。
「……本当はもっと、楽に済ませてあげたかったんだけど」
慈悲深いことを言う鮮花。これは本心からの言葉だった。
鮮花の師である蒼崎橙子曰く、魔術とは常識で可能なことを非常識で可能にしているだけにすぎない。
鮮花は灯油を燃やすために、発火の魔術を火蜥蜴の皮手袋で暴発させ発動させたが、これは魔術でなくてもできることだ。
たとえばこの場合、鮮花がやったことは火をつけるというただ一点だけなのだから、百円ライターでも同じ芸当ができる。
もちろん火力に違いはあるだろうが、鮮花がやったのはあくまでも着火であって、目の前の業火を作り出せたのは灯油の恩恵あってこそ。
鮮花の師である蒼崎橙子曰く、魔術とは常識で可能なことを非常識で可能にしているだけにすぎない。
鮮花は灯油を燃やすために、発火の魔術を火蜥蜴の皮手袋で暴発させ発動させたが、これは魔術でなくてもできることだ。
たとえばこの場合、鮮花がやったことは火をつけるというただ一点だけなのだから、百円ライターでも同じ芸当ができる。
もちろん火力に違いはあるだろうが、鮮花がやったのはあくまでも着火であって、目の前の業火を作り出せたのは灯油の恩恵あってこそ。
魔術師は、魔法使いとは違う。
同様に、魔術は魔法とは違う。
同様に、魔術は魔法とは違う。
どこからともなく炎のドラゴンを呼び出すことも、
手の平に火の弾を作り出しそれを敵に向かって放つことも、
地割れを起こし地中からマグマによる火柱を上げるようなことも、
手袋を嵌めた指先を擦って遠い距離にいる標的を燃やしたりすることも、
魔術師であり、今はしがない魔術遣いでしかない鮮花には、到底無理な芸当なのだった。
手の平に火の弾を作り出しそれを敵に向かって放つことも、
地割れを起こし地中からマグマによる火柱を上げるようなことも、
手袋を嵌めた指先を擦って遠い距離にいる標的を燃やしたりすることも、
魔術師であり、今はしがない魔術遣いでしかない鮮花には、到底無理な芸当なのだった。
そんな鮮花が、魔術を使ってどうやって人を殺せるというのか。
正直、得意の肉弾戦で捻じ伏せていったほうが早いような気もする。
が、知恵を絞ればこうやって、発火の魔術も脅威へと昇華させられる。
鮮花の武器は、百円ライターの皮を被った火炎放射器といったところか。
正直、得意の肉弾戦で捻じ伏せていったほうが早いような気もする。
が、知恵を絞ればこうやって、発火の魔術も脅威へと昇華させられる。
鮮花の武器は、百円ライターの皮を被った火炎放射器といったところか。
とはいえ、やはり鮮花の力では相手を苦しめずに焼き殺すというのも難しい。
そう捉え始めていた頃、
そう捉え始めていた頃、
「……?」
鮮花はようやく、その異変に気づいた。
目の前の炎の中に、あって当然と言えるものがない。
焼くことはできても、焼失は無理だろうと自覚する鮮花は、愕然とした。
炎の中をくまなく探しても、焼け焦げているはずの二つの焼死体が、見つからない。
目の前の炎の中に、あって当然と言えるものがない。
焼くことはできても、焼失は無理だろうと自覚する鮮花は、愕然とした。
炎の中をくまなく探しても、焼け焦げているはずの二つの焼死体が、見つからない。
(まさか)
と鮮花が口に出すよりも先に、
「――『発火能力者(パイロキネシスト)』の方ですの?」
上品な声は背中から、突起物の感触とともに訪れた。
おそるおそる、鮮花が顔だけで後ろを向く。
槍のようなものを構えた少女が一人、立っていた。
おそるおそる、鮮花が顔だけで後ろを向く。
槍のようなものを構えた少女が一人、立っていた。
「可燃性物質などに頼るところから見て、せいぜいが『異能力(レベル2)』あたりのようですわね。
能力者の方ならば、わたくしが『風紀委員(ジャッジメント)』であるということもおわかりになられますでしょう?」
能力者の方ならば、わたくしが『風紀委員(ジャッジメント)』であるということもおわかりになられますでしょう?」
子供っぽいリボンで髪を二つに結った少女は、右袖の腕章を見せつけながら意味のわからない単語を並べた。
場慣れしているのか、刃物を突きつける表情に淀みがない。そして体は、煤の一つもついていなかった。
なぜ――と思案する鮮花に、少女は告げる。
場慣れしているのか、刃物を突きつける表情に淀みがない。そして体は、煤の一つもついていなかった。
なぜ――と思案する鮮花に、少女は告げる。
「とりあえず、大人しくしていただけますかしら。わたくし、あなたとも少しお話がしたいので。もし断るというのであれば……」
「……その槍で、わたしの背中を刺しますか?」
「……その槍で、わたしの背中を刺しますか?」
鮮花の緊迫した問いに、少女はあっけらかんと答える。
「いいえ。そんなことはいたしませんわ。ただ……」
ちらり、と少女が横目をやるその先に、もう一人、白髪の少女が立っていた。
その少女は肩に喇叭状の筒を掲げ、中腰でこちらを向いていた。
あれがなんなのかは、鮮花とて本能で悟らざるを得ない。
あれは重火器――RPG-7だ。
その少女は肩に喇叭状の筒を掲げ、中腰でこちらを向いていた。
あれがなんなのかは、鮮花とて本能で悟らざるを得ない。
あれは重火器――RPG-7だ。
「わたくしの連れが、火力に訴えないとも限りませんの」
後ろの少女は明るく、鮮花にとっては不快極まりない声で警告した。
◇ ◇ ◇
火災現場から少し離れた場所に建つカフェで、白井黒子は放火魔少女の尋問を始めた。
テラスの席に少女を座らせ、丸テーブルを挟んだ向かいの席に自分も座る。隣にはティーもいた。
能力者が相手となっては拘束具などあっても意味を成さないので、少女自身にはなんの枷も嵌めていない。
先ほどは牽制に使った槍も、今は閉まっている。あのようなもの、そもそも白井黒子には不要であるとも言えるのだが。
テラスの席に少女を座らせ、丸テーブルを挟んだ向かいの席に自分も座る。隣にはティーもいた。
能力者が相手となっては拘束具などあっても意味を成さないので、少女自身にはなんの枷も嵌めていない。
先ほどは牽制に使った槍も、今は閉まっている。あのようなもの、そもそも白井黒子には不要であるとも言えるのだが。
「それでは黒桐鮮花さん。あなたがなんの目的でわたくしたちを襲ったのかは、絶対に言えない……いえ、言わないと」
白井黒子の質問に対し、放火魔少女――黒桐鮮花は仏頂面で首肯する。
鮮花が語ったのは己の名前だけで、それ以外の質問については一切黙秘。
襲撃の動機、最終的な目的、他者との面識など、どれだけ尋ねても無視を一貫する。
誰が教えてやるもんか、と言わんばかりの豪気さには、敬服すらしてしまう。
鮮花が語ったのは己の名前だけで、それ以外の質問については一切黙秘。
襲撃の動機、最終的な目的、他者との面識など、どれだけ尋ねても無視を一貫する。
誰が教えてやるもんか、と言わんばかりの豪気さには、敬服すらしてしまう。
「ま、大方ご自身の能力を過信して、趣旨どおりトップに君臨してやろうなどと思った……わけではありませんわね。
あなたは見たところ冷静なようですし、やり口も巧妙。ゲーム感覚、などとは微塵も思っていないのでしょう。
そういった方の目的が、保身などという安易なものであるとは考えられない。
……そういえば、黒桐さんという方はもう一人いらしゃいましたわね。こちらはミキヤ、と読むのかしら?」
あなたは見たところ冷静なようですし、やり口も巧妙。ゲーム感覚、などとは微塵も思っていないのでしょう。
そういった方の目的が、保身などという安易なものであるとは考えられない。
……そういえば、黒桐さんという方はもう一人いらしゃいましたわね。こちらはミキヤ、と読むのかしら?」
名簿を確認しながら、白井黒子は一人熱弁を垂れていく。
そして黒桐幹也の名を告げた瞬間、黒桐鮮花の眉根が釣り上がるのを見逃さなかった。
そして黒桐幹也の名を告げた瞬間、黒桐鮮花の眉根が釣り上がるのを見逃さなかった。
(……ま、そんなことだろうと思いましたけれど)
初めて名簿を見て、御坂美琴の名前を発見したとき。
初対面のティーに対して質問を呈したとき。
双方を思い返して、ため息をつく。
初対面のティーに対して質問を呈したとき。
双方を思い返して、ため息をつく。
「わたくしの能力についてお話しておきましょうか」
白井黒子は唐突に話題を切り替え、手元にプラスチック製のフォークを用意した。
カフェから適当に拝借した、使い捨て上等の品物である。
人肌に突き刺したところで、武器にもなりはしない――白井黒子以外の人間にとっては。
カフェから適当に拝借した、使い捨て上等の品物である。
人肌に突き刺したところで、武器にもなりはしない――白井黒子以外の人間にとっては。
「わたくし、『大能力(レベル4)』の『空間移動能力者(テレポーター)』ですの」
言った瞬間、白井黒子が右手に持っていたフォークが消え、左手に移動していた。
一瞬の出来事に、鮮花の反応は薄い。この手の能力を見るのは初めてなのだろうか。
期待していた反応が得られなかったので、白井黒子はさらに能力を行使する。
左手に持っていたフォークをパッと消し、今度は鮮花の目の前に置く。
それをまた右手で掴むと、瞬時に左手の中に消して移した。
一瞬の出来事に、鮮花の反応は薄い。この手の能力を見るのは初めてなのだろうか。
期待していた反応が得られなかったので、白井黒子はさらに能力を行使する。
左手に持っていたフォークをパッと消し、今度は鮮花の目の前に置く。
それをまた右手で掴むと、瞬時に左手の中に消して移した。
「おわかりいただけましたかしら。炎から逃れたトリックもこれですわ」
ふっと消え、現れる。
線での移動を、点での移動に切り替える。
これこそ、白井黒子が得意とする『空間移動(テレポート)』だ。
信じられない、といった様子で固まる鮮花を尻目に、白井黒子は続ける。
線での移動を、点での移動に切り替える。
これこそ、白井黒子が得意とする『空間移動(テレポート)』だ。
信じられない、といった様子で固まる鮮花を尻目に、白井黒子は続ける。
「あなたに武器も向けていない理由もこれですのよ? たとえば、なんの変哲もないこのフォーク。
これを瞬時に、あなたの体の中に移すことができると言ったら――それだけで警告は済みますもの。
そしてわたくしは今、改めてあなたに命令しますの。――あなたの目的をお吐きなさい」
これを瞬時に、あなたの体の中に移すことができると言ったら――それだけで警告は済みますもの。
そしてわたくしは今、改めてあなたに命令しますの。――あなたの目的をお吐きなさい」
キッと鮮花を睨み据える白井黒子。
両者は干渉し合っていないはずなのに、彼女だけは相手を容易に害することができる。
それは愕然とした表情の鮮花にも伝わっているのだろう。ごくり、と生唾を飲み込む音とて聞こえた。
両者は干渉し合っていないはずなのに、彼女だけは相手を容易に害することができる。
それは愕然とした表情の鮮花にも伝わっているのだろう。ごくり、と生唾を飲み込む音とて聞こえた。
……おそらくこの少女は、自分ではない誰かのために戦いを選択したのだ。
可能性としては、同じ姓を持つ黒桐幹也のためか、それとも別の人間のためか。
白井黒子が御坂美琴に抱いた、『生かしたい』という想いを、鮮花は行動に移したのだろう。
他者を殺してでも、自分の命を投げ出してでも、生きてほしい人が――彼女には、確かにいる。
可能性としては、同じ姓を持つ黒桐幹也のためか、それとも別の人間のためか。
白井黒子が御坂美琴に抱いた、『生かしたい』という想いを、鮮花は行動に移したのだろう。
他者を殺してでも、自分の命を投げ出してでも、生きてほしい人が――彼女には、確かにいる。
「……逆に尋ねますが」
しばらくして、鮮花は口を開いた。
毅然とした声が、白井黒子に質問を寄越す。
毅然とした声が、白井黒子に質問を寄越す。
「生き残りは一人と決められたこのゲームで……白井さんはいったいなにをお望みなんですか?」
質問は質問で返ってきた。
白井黒子は鮮花の物怖じしない様に多少イラッとしつつも、すぐに答える。
白井黒子は鮮花の物怖じしない様に多少イラッとしつつも、すぐに答える。
「少なくとも、誰かを犠牲になどとは考えておりません。期限ギリギリまで、別の可能性を模索し――」
「あ、そっか。やっぱり、そうなんだ」
「あ、そっか。やっぱり、そうなんだ」
言い終わるよりも先に、鮮花が口を挟んだ。
吐き出す言葉に、不適な笑みを添えて。
吐き出す言葉に、不適な笑みを添えて。
「別の可能性だなんて、ちゃんちゃらおかしいです。そんなのは、問題の先送りでしかない。
だって、わたしたちはもう既に『負け』ているんですもの。
勝敗が決しているのに駄々をこねるなんて、子供か馬鹿のすることよ。
ううん。あなたはたぶん、ただ単純に『覚悟』がなってないだけ。ねぇ?」
だって、わたしたちはもう既に『負け』ているんですもの。
勝敗が決しているのに駄々をこねるなんて、子供か馬鹿のすることよ。
ううん。あなたはたぶん、ただ単純に『覚悟』がなってないだけ。ねぇ?」
言って、鮮花はその場から立ち上がった。
白井黒子はこの瞬間、宣言どおり鮮花の体内にフォークを転移させることが可能だった。
なのに、それをしなかった。初めから、できるはずもなかった。
白井黒子はこの瞬間、宣言どおり鮮花の体内にフォークを転移させることが可能だった。
なのに、それをしなかった。初めから、できるはずもなかった。
「先輩として教えてあげる。覚悟のない脅しに屈するほど、わたしは弱くない――っ!」
言い放ち、鮮花はテーブルに向かって拳を突き落とした。
火蜥蜴の皮手袋が嵌められた、右の拳を。
火蜥蜴の皮手袋が嵌められた、右の拳を。
「AzoLto――――!」
拳がテーブルに着弾すると同時、鮮花は呪文を詠唱した。
大気が燃え上がる。木製のテーブルを巻き込み、周りにいた少女たちの驚きを孕みながら。
眼前の火の手から逃れるため、白井黒子は隣のティーを抱きかかえると、その場から消えた。
カフェテラスから少しばかり離れたところに現れ、着地する。
大気が燃え上がる。木製のテーブルを巻き込み、周りにいた少女たちの驚きを孕みながら。
眼前の火の手から逃れるため、白井黒子は隣のティーを抱きかかえると、その場から消えた。
カフェテラスから少しばかり離れたところに現れ、着地する。
この瞬間、白井黒子は鮮花への攻撃ではなく、危機からの退避を優先したのだ。
相対すべき『敵』の選択を確認してから、鮮花は彼女たちとは逆方向に走った。
相対すべき『敵』の選択を確認してから、鮮花は彼女たちとは逆方向に走った。
「逃しませんわ!」
白井黒子は叫び、鮮花の行く手を遮るため彼女の目の前に転移する。
鮮花は怯まなかった。むしろ予想していたのか。動作は驚くほど流麗だった。
鮮花は怯まなかった。むしろ予想していたのか。動作は驚くほど流麗だった。
「なっ――」
鮮花は、逃走の邪魔者を排除せんと、軽やかに身を翻した。
白井黒子が相手を拘束するために腕を取るよりも速く、しなやかな脚は頭上まで上がる。
白井黒子が相手を拘束するために腕を取るよりも速く、しなやかな脚は頭上まで上がる。
――頭の上から、黒桐鮮花必殺のネリチャギ(かかと落とし)が降ってきた。
思わぬ攻撃に、白井黒子は両腕を交差させこれを防ぐ。
鈍い音が響き、ガードは一撃で解かれた。
それどころか衝撃も殺しきれず、白井黒子はその場で尻餅をついてしまう。
絶好の好機が生まれ、しかし鮮花は逃走を再開した。
鈍い音が響き、ガードは一撃で解かれた。
それどころか衝撃も殺しきれず、白井黒子はその場で尻餅をついてしまう。
絶好の好機が生まれ、しかし鮮花は逃走を再開した。
「くっ……!」
すぐさま身を起こし、鮮花の後ろ姿を目で捉える白井黒子。
脱兎のごとき全力疾走は、見る見るうちに遠ざかる。
それでも、まだテレポートの効果範囲内だった。
脱兎のごとき全力疾走は、見る見るうちに遠ざかる。
それでも、まだテレポートの効果範囲内だった。
「……っ」
跳べば、一瞬で追いつける。
なのに、白井黒子はそれ以上鮮花を追わなかった。
追ったところでまたネリチャギが飛んでくると思ったわけではない。
なのに、白井黒子はそれ以上鮮花を追わなかった。
追ったところでまたネリチャギが飛んでくると思ったわけではない。
――覚悟のない脅しに屈するほど、わたしは弱くない。
白井黒子を止めていたのは、鮮花が言い放ったあの言葉だった。
覚悟のない脅し――そんな馬鹿な、と白井黒子は首を振る。
これまでも、『風紀委員(ジャッジメント)』として多くの能力者たちを拘束してきた彼女だ。
それが今さら、他者を害することに覚悟がないなど、
覚悟のない脅し――そんな馬鹿な、と白井黒子は首を振る。
これまでも、『風紀委員(ジャッジメント)』として多くの能力者たちを拘束してきた彼女だ。
それが今さら、他者を害することに覚悟がないなど、
「……屈辱、ですわね」
いや、嘘だ。
この場において、拘束などという生ぬるい判断をしてしまったのがそもそものミス。
黒桐鮮花はつまり、こう言いたかったのだろう。
この場において、拘束などという生ぬるい判断をしてしまったのがそもそものミス。
黒桐鮮花はつまり、こう言いたかったのだろう。
――殺す覚悟もない偽善者に、わたしの想いは止められない。
黒桐鮮花は、ありとあらゆる意味で本気だったのだ。
学園都市の不良などとは、比べるのも失礼なほどに『覚悟』が違う。
そしてその覚悟のほどは、問題の先延ばしをしている白井黒子と比したとしても、上をいくのだろう。
学園都市の不良などとは、比べるのも失礼なほどに『覚悟』が違う。
そしてその覚悟のほどは、問題の先延ばしをしている白井黒子と比したとしても、上をいくのだろう。
「……ッ!」
追えない。
追えるはずがなかった。
少なくとも、今は。
白井黒子に、黒桐鮮花の暴走は止められない。
◇ ◇ ◇
白井黒子が地面に向かって拳を叩きつけるのを、ティーは確かに見た。
「…………」
燃え盛るカフェテーブルと、鮮花が逃げていった方向、そして白井黒子を順に見回していく。
言葉はない。感慨はある。ただ、表には出さない。
言葉はない。感慨はある。ただ、表には出さない。
内に秘めた感慨は、白井黒子には決して伝わらないだろう。
伝えるべきでも、ないのかもしれない。
寡黙かそうでないかを考えるまでもなく、今の彼女にかけるべき言葉など存在しないのだ。
伝えるべきでも、ないのかもしれない。
寡黙かそうでないかを考えるまでもなく、今の彼女にかけるべき言葉など存在しないのだ。
少なくとも、ティーはそのように考える。考えているように、見える。
とてとてと、悔しそうな白井黒子の背中に歩み寄りながら。
ティーは、やはりあの場で発射しておくべきだったと後悔した。
とてとてと、悔しそうな白井黒子の背中に歩み寄りながら。
ティーは、やはりあの場で発射しておくべきだったと後悔した。
【D-5/三角州近辺・カフェ前/一日目・黎明】
【白井黒子@とある魔術の禁書目録】
[状態]:健康
[装備]:グリフォン・ハードカスタム@戯言シリーズ、地虫十兵衛の槍@甲賀忍法帖
[道具]:デイパック、支給品一式、不明支給品0~1
[思考・状況]
基本:ギリギリまで「殺し合い以外の道」を模索する。
0:屈辱と敗北感。己を見つめなおす……?
1:当面、ティー(とシャミセン)を保護する。可能ならば、シズか(もし居るなら)陸と会わせてやりたい。
2:できれば御坂美琴か上条当麻と合流したい。美琴や当麻でなくとも、信頼できる味方を増やしたい。
3:夜が明けてから、もう一度『黒い壁』が本当に存在するのかどうかを見てみる。
[備考]:
※『空間移動(テレポート)』の能力が少し制限されている可能性があります。
現時点では、彼女自身にもストレスによる能力低下かそうでないのか判断がついていません。
※黒桐鮮花を『異能力(レベル2)』の『発火能力者(パイロキネシスト)』だと誤解しています。
[状態]:健康
[装備]:グリフォン・ハードカスタム@戯言シリーズ、地虫十兵衛の槍@甲賀忍法帖
[道具]:デイパック、支給品一式、不明支給品0~1
[思考・状況]
基本:ギリギリまで「殺し合い以外の道」を模索する。
0:屈辱と敗北感。己を見つめなおす……?
1:当面、ティー(とシャミセン)を保護する。可能ならば、シズか(もし居るなら)陸と会わせてやりたい。
2:できれば御坂美琴か上条当麻と合流したい。美琴や当麻でなくとも、信頼できる味方を増やしたい。
3:夜が明けてから、もう一度『黒い壁』が本当に存在するのかどうかを見てみる。
[備考]:
※『空間移動(テレポート)』の能力が少し制限されている可能性があります。
現時点では、彼女自身にもストレスによる能力低下かそうでないのか判断がついていません。
※黒桐鮮花を『異能力(レベル2)』の『発火能力者(パイロキネシスト)』だと誤解しています。
【ティー@キノの旅】
[状態]:健康。
[装備]:RPG-7(1発装填済み)@現実、シャミセン@涼宮ハルヒの憂鬱
[道具]:デイパック、支給品一式、RPG-7の弾頭×2、不明支給品0~1
[思考・状況]
基本:???
1.RPG-7を使ってみたい。
2.手榴弾やグレネードランチャー、爆弾の類でも可。むしろ色々手に入れて試したい。
3.シズか(もし居るなら)陸と合流したい。そのためにも当面、白井黒子と行動を共にしてみる。
[備考]:
※ティーは、キノの名前を素で忘れていたか、あるいは、素で気づかなかったようです。
[状態]:健康。
[装備]:RPG-7(1発装填済み)@現実、シャミセン@涼宮ハルヒの憂鬱
[道具]:デイパック、支給品一式、RPG-7の弾頭×2、不明支給品0~1
[思考・状況]
基本:???
1.RPG-7を使ってみたい。
2.手榴弾やグレネードランチャー、爆弾の類でも可。むしろ色々手に入れて試したい。
3.シズか(もし居るなら)陸と合流したい。そのためにも当面、白井黒子と行動を共にしてみる。
[備考]:
※ティーは、キノの名前を素で忘れていたか、あるいは、素で気づかなかったようです。
◇ ◇ ◇
三角州上の分岐路を左に折れ、黒桐鮮花は川を渡った。
息を切らすほどの全力疾走で逃げ回り、追ってくる気配がないと判断したところで止まる。
十字路の辺りまで来ていた。両膝に手をつき、懸命に息を整えようとしながら、鮮花は思う。
息を切らすほどの全力疾走で逃げ回り、追ってくる気配がないと判断したところで止まる。
十字路の辺りまで来ていた。両膝に手をつき、懸命に息を整えようとしながら、鮮花は思う。
「……覚悟がなってないのは、わたしも同じ」
逆襲ではなく、敗走を選び取ってしまった自分を鑑みて、悔しそうに呟く。
あの瞬間、白井黒子の不意は確かにつけたはずなのに。鮮花は、逃げに回ってしまった。
勝ち目が薄そうだったから、相手が二人だったから、そういった負け惜しみを言うつもりもない。
あの瞬間、白井黒子の不意は確かにつけたはずなのに。鮮花は、逃げに回ってしまった。
勝ち目が薄そうだったから、相手が二人だったから、そういった負け惜しみを言うつもりもない。
(ここには、式や藤乃もいる……なのにわたしは、幹也を生かそうとしているんだ。
いざ会ってから考える、なんていうのは完璧なまでに『逃げ』だもの。
なってない。わたしは、彼女のことを言えないくらい……なってない)
いざ会ってから考える、なんていうのは完璧なまでに『逃げ』だもの。
なってない。わたしは、彼女のことを言えないくらい……なってない)
こちらの命令に背いたら殺す。
そういった脅迫のシーンはドラマなどでもよく見かけられるが、意外と実行に移せないものだ。
白井は見るからにその典型だった。
脅しはすれど、本気ではない。人を殺す覚悟など、そう簡単にできるものではないのだから。
そういった脅迫のシーンはドラマなどでもよく見かけられるが、意外と実行に移せないものだ。
白井は見るからにその典型だった。
脅しはすれど、本気ではない。人を殺す覚悟など、そう簡単にできるものではないのだから。
では自分は、と鮮花は考える。
黒桐幹也を生かすためならば、それ以外の人間が死のうが構わないし、自らが殺して回ることも苦ではない。
それは白井の警告と同様、決意の話であって、実際にやり遂げられるかは――
黒桐幹也を生かすためならば、それ以外の人間が死のうが構わないし、自らが殺して回ることも苦ではない。
それは白井の警告と同様、決意の話であって、実際にやり遂げられるかは――
(いいえ)
――出かかっていた答えを、鮮花は寸前で飲み込んだ。
やれるかやれないか、ではない。
やるんだ。
だが。
やれるかやれないか、ではない。
やるんだ。
だが。
(式も、藤乃も……わたしが……っ)
黒桐鮮花は、自身が禁忌に惹かれる質であることを自覚している。
だからこそ、戸籍上は兄に分類される黒桐幹也を、心の底から愛せるのだ。
ただ、だからといって友人や他人を殺せるかと自問すれば、答えは出ない。
近親への恋情と殺人を同列に扱うこと自体が間違っているのか、鮮花は懊悩を繰り返す。
だからこそ、戸籍上は兄に分類される黒桐幹也を、心の底から愛せるのだ。
ただ、だからといって友人や他人を殺せるかと自問すれば、答えは出ない。
近親への恋情と殺人を同列に扱うこと自体が間違っているのか、鮮花は懊悩を繰り返す。
(……あったまくるなぁ)
魔術を始めたのも、そもそもが幹也に並び立とうとしたのがきっかけだった。
両儀式などという反則紛いの女に、対抗心を燃やしていたのもある。
決して殺しの道具にしたかったわけでは、ない。
両儀式などという反則紛いの女に、対抗心を燃やしていたのもある。
決して殺しの道具にしたかったわけでは、ない。
(火蜥蜴の皮手袋が私に配られてたのは、籤運が良かったわけじゃない……これはたぶん、皮肉。
この程度の力じゃわたしは式にも勝てないし、藤乃を見捨てるような覚悟もない。
あるのはただ、幹也に死んでほしくない、っていうちっぽけな想いだけなんだ)
この程度の力じゃわたしは式にも勝てないし、藤乃を見捨てるような覚悟もない。
あるのはただ、幹也に死んでほしくない、っていうちっぽけな想いだけなんだ)
そこで、黒桐鮮花は一度認めてしまう。
このやり方では、ダメ。
いずれは最悪の形で破綻する。
その未来が見えたから、鮮花は思い切り悔しがるのだ。
固く握られた右拳は、手袋をしていなかったら血が出ていたと思う。
このやり方では、ダメ。
いずれは最悪の形で破綻する。
その未来が見えたから、鮮花は思い切り悔しがるのだ。
固く握られた右拳は、手袋をしていなかったら血が出ていたと思う。
「……っ」
気分は最悪だった。今は誰の顔も見たくない。
そんなときに限って、出会いはやって来る。
そんなときに限って、出会いはやって来る。
「――あー、ラブコメしたいぜい」
見晴らしもいい交差点で、その男は平日に街をぶらつくチンピラの装いで歩いていた。
派手な金髪にサングラスとアロハシャツの姿は、鮮花に最悪の第一印象を与える。
派手な金髪にサングラスとアロハシャツの姿は、鮮花に最悪の第一印象を与える。
「どこかに素敵な出会いでも転がっていないかにゃー。突然『あたしお兄ちゃんの妹なんですー』とか告白されても大歓迎ぜよ」
男性の友人などろくにいない鮮花である。こういう手合いが得意であるはずもない。
金髪アロハは戯言を吐きながら、なおも鮮花に近づいてい来る。どういうわけか、こちらに気づかぬ振りをしながら。
金髪アロハは戯言を吐きながら、なおも鮮花に近づいてい来る。どういうわけか、こちらに気づかぬ振りをしながら。
「妹のみならず、先輩後輩先生クラスメイトに委員長幼馴染寮の管理人その他諸々手広く大歓迎だぜい。
空から女の子が振ってきて家のベランダに引っかかってるっていうのも――おっと、噂をすれば可愛い子発見ぜよ」
「……おちょくってるんですか?」
空から女の子が振ってきて家のベランダに引っかかってるっていうのも――おっと、噂をすれば可愛い子発見ぜよ」
「……おちょくってるんですか?」
鮮花も鮮花で、身を隠したり即座に撃退しようとしたりはしなかった。
金髪アロハの目的が不明瞭だったこともあるし、なにより今は気疲れ中だ。
適当にやりすごそう。しつこいようなら金的の一つでもくれてやろう。腹癒せくらいにはなる。
そう思って、
金髪アロハの目的が不明瞭だったこともあるし、なにより今は気疲れ中だ。
適当にやりすごそう。しつこいようなら金的の一つでもくれてやろう。腹癒せくらいにはなる。
そう思って、
「つれないにゃー。さりげなーく声をかけるのは、ガールズ・ハントの基本ぜよ」
「――そそ。相手がお嬢様っぽい子だったらなおのこと、出会い方にゃ気を配らないとな」
「――そそ。相手がお嬢様っぽい子だったらなおのこと、出会い方にゃ気を配らないとな」
眉根を吊り上げる鮮花は、ハッとした。
男の声が二人分、重なる。
一つは、眼前の金髪アロハから。
そしてもう一つ、後ろからも声が。
男の声が二人分、重なる。
一つは、眼前の金髪アロハから。
そしてもう一つ、後ろからも声が。
「カワイコちゃん相手に、本当の意味でのハンティング……なんて真似はしたくねーんだわ」
鮮花の後ろで銃を構えるその男も、軽薄な印象満点の金髪姿だった。
いや、この際髪の色などどうでもいい。
問題なのは、彼の構える銃口が、鮮花のほうに向いているという点だ。
いや、この際髪の色などどうでもいい。
問題なのは、彼の構える銃口が、鮮花のほうに向いているという点だ。
(――やられた)
少しばかり目立つ場所で気落ちしていたとはいえ、鮮花はものの見事に挟まれてしまったのである。
この、常に気を張り続けなければいけない状況下で。
それも、幹也以外の男性二人に。
この、常に気を張り続けなければいけない状況下で。
それも、幹也以外の男性二人に。
「んー? なんか空気がぴりぴりしてるぜい。クルツ、やっぱそりゃ女の子に向けるもんじゃねーぜよ」
「おっと、下手に威嚇しちまったか。まあそうびくびくしなさんな。お兄さんたちはいたって親切な――」
「おっと、下手に威嚇しちまったか。まあそうびくびくしなさんな。お兄さんたちはいたって親切な――」
どうして、気が立っているときに限って。
こうも、神経を逆なでするような出来事が。
こうも、神経を逆なでするような出来事が。
「――――っ」
刹那、鮮花の中でなにかが弾けた。
体温計が高熱によってパリンと割れる、そんなイメージだ。
沸点を越えた怒りは熱を膨張させ、煮え湯を炎へと昇華させる。
体温計が高熱によってパリンと割れる、そんなイメージだ。
沸点を越えた怒りは熱を膨張させ、煮え湯を炎へと昇華させる。
皮手袋に覆われた右手が、大気に触れている。
口はぶつぶつと呪文を唱え続け、前後の二人は止めもしない。
それだけで、燃焼を起こすには十分だった。
鮮花の魔術は、発動だけならば容易なのだから。
燃やす対象は、空気中の酸素だ。
口はぶつぶつと呪文を唱え続け、前後の二人は止めもしない。
それだけで、燃焼を起こすには十分だった。
鮮花の魔術は、発動だけならば容易なのだから。
燃やす対象は、空気中の酸素だ。
「おわっ!?」
どちらからでもなく、驚いた男の声が上がった。
鮮花の右手から、唐突に炎が迸ったからである。
それはどちらを焼くこともなくすぐに消えたが、二人としても見逃せるようなものではない。
鮮花の右手から、唐突に炎が迸ったからである。
それはどちらを焼くこともなくすぐに消えたが、二人としても見逃せるようなものではない。
これは、テレポートなどという『魔法』のような力を振り翳していた白井黒子のものとは違う。
あなたたちのようないけ好かない男を丸焼きにするくらいの覚悟なら、とうにできている――という、鮮花なりの警告だ。
あなたたちのようないけ好かない男を丸焼きにするくらいの覚悟なら、とうにできている――という、鮮花なりの警告だ。
「なんのつもりか知らないけれど、わたし今ムシャクシャしてるの。
これ以上話しかけてくるって言うんなら、馴れ馴れしいほうから黒こげにするから――!」
これ以上話しかけてくるって言うんなら、馴れ馴れしいほうから黒こげにするから――!」
憂さを晴らすかのごとく叫ぶ。
前の金髪アロハ、クルツと呼ばれた後ろの金髪も、揃って唖然としていた。
種も仕掛けもある鮮花の魔術は、一般人から見れば手品としか映らないだろうか。
そうやって嘲笑うなら好都合だ。相手が軟派な男共なら、容赦なく焼れるような気がするから。
前の金髪アロハ、クルツと呼ばれた後ろの金髪も、揃って唖然としていた。
種も仕掛けもある鮮花の魔術は、一般人から見れば手品としか映らないだろうか。
そうやって嘲笑うなら好都合だ。相手が軟派な男共なら、容赦なく焼れるような気がするから。
「能力者……いや、どちらかというと魔術師のほうが近い、か?」
早速、金髪アロハがなにか呟いた。反射的に、鮮花が右手を伸ばす。
しかし金髪アロハから軽薄な雰囲気は消えていて、さらに発した言葉の中の『魔術師』という単語が、鮮花を抑制した。
この男は、魔術を知っているのだろうか――?
しかし金髪アロハから軽薄な雰囲気は消えていて、さらに発した言葉の中の『魔術師』という単語が、鮮花を抑制した。
この男は、魔術を知っているのだろうか――?
「つーとなんだ。土御門のご同輩かなんかか? ま、俺としちゃそれでも全然構わねーけど」
「むしろ好都合だにゃー。あー、お嬢さん? 俺の名前は土御門元春。たぶん、おたくと同じそっち側の人間ぜよ」
「あ、俺はクルツね」
「むしろ好都合だにゃー。あー、お嬢さん? 俺の名前は土御門元春。たぶん、おたくと同じそっち側の人間ぜよ」
「あ、俺はクルツね」
あたりまえだが、聞かない名前だった。
ただ、この土御門なる男が言う『そっち側』とは、間違いなく『魔術師の側』を指している。
だからといって警戒の対象から外れるはずもないが――鮮花の興味は今、確かにそそられてしまっていた。
ただ、この土御門なる男が言う『そっち側』とは、間違いなく『魔術師の側』を指している。
だからといって警戒の対象から外れるはずもないが――鮮花の興味は今、確かにそそられてしまっていた。
「立ち話もなんだ。どこか入ってゆっくりと、ってのが俺としては望ましいんだけどな。どうだい?」
鮮花の魔術に一旦は驚いた素振りを見せたクルツも、すぐに飄々とした態度を取り戻す。
「あ、ちなみにこれ、本物じゃなくエアガンだから」
最初から殺意はなかった、と今さら説明して、クルツはエアガンをしまい込む。
この二人に害意があったとするならば、まず二人で組んでいること自体が不自然だ。
生き残るのは一人。それを重く受け止めている鮮花だからこそ、二人の目的は単純なものではないと踏んでいた。
この二人に害意があったとするならば、まず二人で組んでいること自体が不自然だ。
生き残るのは一人。それを重く受け止めている鮮花だからこそ、二人の目的は単純なものではないと踏んでいた。
「……まあ、いいですけど」
――方針を見直すべきかもしれない。
自分にあるのは愛情だけで、実力も覚悟はまだ足りていない。
それを実感した鮮花には、今一度未来を思案する時間が必要だった。
一人で延々と考え込むよりは、魔術を知る者と交流したほうがなにか見えてくるものがあるかもしれない。
……片方は、余計だが。
自分にあるのは愛情だけで、実力も覚悟はまだ足りていない。
それを実感した鮮花には、今一度未来を思案する時間が必要だった。
一人で延々と考え込むよりは、魔術を知る者と交流したほうがなにか見えてくるものがあるかもしれない。
……片方は、余計だが。
「オーケイ。では早速、君のお名前なんかを聞かせ――ぐぼぁ!?」
気安く肩に触れようとしたクルツに対し、鮮花は冷徹な表情で裏券を見舞った。
顔面直撃。仰向けに倒れる軟派男。相方らしい土御門も、ドッと笑う。
顔面直撃。仰向けに倒れる軟派男。相方らしい土御門も、ドッと笑う。
(なんて、不潔――――ッ!)
黒桐鮮花は、頭を抱えて慨嘆した。
【D-5/十字路/一日目・黎明】
【黒桐鮮花@空の境界】
[状態]:疲労(小)
[装備]:火蜥蜴の革手袋@空の境界
[道具]:デイパック、支給品一式
[思考・状況]
基本:黒桐幹也をなんとしても生かしたい。
1:具体的な方針を練り直す。判断材料として、土御門とクルツの誘いに乗る。
[備考]
※「忘却録音」終了後からの参戦。
[状態]:疲労(小)
[装備]:火蜥蜴の革手袋@空の境界
[道具]:デイパック、支給品一式
[思考・状況]
基本:黒桐幹也をなんとしても生かしたい。
1:具体的な方針を練り直す。判断材料として、土御門とクルツの誘いに乗る。
[備考]
※「忘却録音」終了後からの参戦。
【クルツ・ウェーバー@フルメタル・パニック!】
[状態]:左腕に若干のダメージ
[装備]:エアガン(12/12)
[道具]デイパック、支給品一式、缶ジュース×20(学園都市製)@とある魔術の禁書目録、BB弾3袋
[思考・状況]
基本:生き残りを優先する。宗介、かなめ、テッサ、当麻、インデックス、との合流を目指す。
1:鮮花とお話し、彼女を仲間に引き入れる。
2:可愛いい女の子か使える人間は仲間に引き入れ、その他の人間は殺して装備を奪う。
3:知り合いが全滅すれば優勝を目指すという選択肢もあり。
4:南回りでE-3へ。その後、E-4ホールに向かいステイルと合流する。
5:ガウルンに対して警戒。
【備考】
※土御門から“とある魔術の禁書目録”の世界観、上条当麻、禁書目録、ステイル=マグヌスとその能力に関する情報を得ました。
[状態]:左腕に若干のダメージ
[装備]:エアガン(12/12)
[道具]デイパック、支給品一式、缶ジュース×20(学園都市製)@とある魔術の禁書目録、BB弾3袋
[思考・状況]
基本:生き残りを優先する。宗介、かなめ、テッサ、当麻、インデックス、との合流を目指す。
1:鮮花とお話し、彼女を仲間に引き入れる。
2:可愛いい女の子か使える人間は仲間に引き入れ、その他の人間は殺して装備を奪う。
3:知り合いが全滅すれば優勝を目指すという選択肢もあり。
4:南回りでE-3へ。その後、E-4ホールに向かいステイルと合流する。
5:ガウルンに対して警戒。
【備考】
※土御門から“とある魔術の禁書目録”の世界観、上条当麻、禁書目録、ステイル=マグヌスとその能力に関する情報を得ました。
【土御門元春 @とある魔術の禁書目録】
[状態]:健康
[装備]:なし
[道具]:デイパック、支給品一式、不明支給品1~3
[思考・状況]
基本:生き残りを優先する。宗介、かなめ、テッサ、当麻、インデックス、との合流を目指す。
1:鮮花の発火能力に興味。話を聞き、その素性を調べる。
2:可愛いい女の子か使える人間は仲間に引き入れ、その他の人間は殺して装備を奪う。ただし御坂美琴に関しては単独行動していたら接触しない。
3:南回りでE-3へ。その後、E-4ホールに向かいステイルと合流する。
4:最悪最後の一人を目指すことも考慮しておく。
【備考】
※クルツから“フルメタル・パニック!”の世界観、相良宗介、千鳥かなめ、テレサ・テスタロッサに関する情報を得ました。
※主催陣は死者の復活、並行世界の移動、時間移動のいずれかの能力を持っていると予想しましたが、誰かに伝えるつもりはありません。
[状態]:健康
[装備]:なし
[道具]:デイパック、支給品一式、不明支給品1~3
[思考・状況]
基本:生き残りを優先する。宗介、かなめ、テッサ、当麻、インデックス、との合流を目指す。
1:鮮花の発火能力に興味。話を聞き、その素性を調べる。
2:可愛いい女の子か使える人間は仲間に引き入れ、その他の人間は殺して装備を奪う。ただし御坂美琴に関しては単独行動していたら接触しない。
3:南回りでE-3へ。その後、E-4ホールに向かいステイルと合流する。
4:最悪最後の一人を目指すことも考慮しておく。
【備考】
※クルツから“フルメタル・パニック!”の世界観、相良宗介、千鳥かなめ、テレサ・テスタロッサに関する情報を得ました。
※主催陣は死者の復活、並行世界の移動、時間移動のいずれかの能力を持っていると予想しましたが、誰かに伝えるつもりはありません。
| 前:摩天楼狂笑曲 | 白井黒子 | 次:明日のきみと逢う為に |
| 前:摩天楼狂笑曲 | ティー | 次:明日のきみと逢う為に |
| 前:摩天楼狂笑曲 | 黒桐鮮花 | 次:明日の君と逢うために |
| 前:戦場という日常 | クルツ・ウェーバー | 次:明日の君と逢うために |
| 前:戦場という日常 | 土御門元春 | 次:明日の君と逢うために |